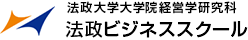HBSインタビュー

岸本直樹先生
アメリカのビジネススクールを経て法政へ
法政大学大学院経営学研究科教授
2004年度 経営学研究科長
岸本直樹先生
―研究をはじめたきっかけ、研究者になった経緯を教えてください。
東京大学経済学部で履修した科目のうち、一番面白かったのは会計学がご専門の諸井勝之助先生が担当された「経営財務」でした。その影響もあり、卒業後は証券会社に就職しましたが、入社一年目にニューヨークの事務所に派遣となり、ワールド・トレード・センター内の高層ビルで働くことになりました。当時のアメリカでは、ファイナンスの研究者が有力な証券会社に移って活躍する流れができ始めていました。私もこの流れに触発されて、ちょうどワールド・トレード・センターのすぐ近くにニューヨーク大学(New York University、 NYU)のビジネスクールがありましたので、その博士課程に応募してみました。当時のアメリカの博士課程には、ティーチング・アシスタントあるいはリサーチ・アシスタントと学費の全額免除がセットでオファーされる制度がありました。幸い、私もそのオファーをいただきましたので、会社を辞めて博士課程に入学しました。入学後は、大学所有のアパートに住ませてもらい、土曜日だけ開校される日本人学校で中学生に教えたりしながら、勉強に励みました。
修士課程ではなく、直接博士課程に進学されたのですか。
アメリカのビジネススクールの博士課程は5年一貫なんですね。ですが、途中でコンプリヘンシブ・エグザム(comprehensive examination)という総合試験があり、それに合格すると修士号が授与されるので、私は修士号も持っています。博士課程で開講されている科目の授業内容はレベルが高いですし、毎週宿題が沢山出る科目もありましたので、必死で勉強しました。その結果、5年後には、「金利リスクと資産価格リスクに依存するオプションの価格付け」というタイトルの博士論文を完成することができ、晴れて博士号を取得することができました。
博士号取得後は、アメリカで研究を続けられたのですか。
博士課程修了後、デューク大学(Duke University)のビジネススクール(The Fuqua School of Business)でアシスタント・プロフェッサーのポストを得ました。このビジネススクールは、全米にある800以上のビジネススクールの中でもトップスクールに位置づけられていまして、私はその中のファイナンス・グループに属しました。日本の大学とは異なり、アメリカの有力なビジネススクールでは研究と教育以外の仕事はほとんどありません。財政基盤がしっかりしており、良い研究者や学生が集まっていますから、教員が研究と教育に集中できる環境が整っているんですね。このようなトップスクールのMBAプログラムのカリキュラムには、どのスクールでも開講する基本的な科目が含まれていまして、ファイナンス分野にもそのような定番科目が5、6科目あります。私は、そのうちの2、3科目を受け持っていました。
デューク大学のビジネススクールで5年ほど教えた後、日本に帰国し、筑波大学社会工学系でポストを得ました。社会工学系は理系でしたので、実験室が各教員に割り当てられていて、学生と教員の比率も文系とは大きく異なります。私はファイナンス系の講義科目を担当し、それ以外にも、一人か二人の学部生の卒業研究の指導と、一人前後の修士課程の学生の修士論文指導を毎年担当しました。筑波大学には約10年間在籍し、その後縁あって法政に移ってきました。
ご専門の研究領域について教えていただけますか。
ファイナンスの主要テーマは、企業あるいは個人の、資金運用(=投資)と資金調達です。さて、この資金運用と資金調達を結び付けているのは金融商品です。すなわち、金融商品を買うことが資金運用ですし、金融商品を発行することが資金調達です。つまり、両者の仲介を担っているのが金融商品です。ところで、資金運用する場合も、資金調達する場合も、重要な関心事は金融商品の価格です。例えば、株式投資では株価が安い時に買い、高い時に売ると儲かりますし、資金調達のためローンを組む場合は、金利が安い時に借りた方が良いですよね。したがって、かねてよりファイナンスの研究の中心は金融商品の価格付けでした。ちなみに、金融商品の例としては、まずは金利商品である債券とローンがあり、次に株式、それからまとめてデリバティブと言いますが、先物、スワップ、オプションがあります。私は、これら金融商品の価格付けの研究をしてきました。
研究分野はビジネススクールでの教育にどう関連しているのですか。
アメリカのビジネススクールでは主要な分野、例えば、組織マネジメント、経営戦略論、ファイナンス、マーケティング、会計学、経済学、それからツール科目に位置づけられるオペレーションズ・マネジメントや統計学、さらにマネジメント・インフォメーション・システムには一定数の教員を配置しています。デューク大学にも、ファイナンス科目を教える教員が10人くらいいて、ファイナンスの基礎的な科目と選択科目を教えていました。ファイナンスの基礎科目としては、インベストメントという金融商品の分析を学ぶ科目と、コーポレート・ファイナンスという企業財務を学ぶ科目があります。私はデューク大学で、インベストメントの選択科目と、学部生向けのコーポレート・ファイナンスの入門科目を担当しました。
筑波大学でも同じような科目を教えておられたのでしょうか。
筑波大学は国立大学でしかも私は理系の部局に所属していましたので、私の担当科目は少なかったですね。学部や大学院のファイナンスの入門科目、論文の指導、それから他の教員と分担してデータ分析の実習科目を受け持っていました。
法政大学ではどのような科目を担当されましたか。
法政に移ってからは様々な科目を担当しました。大学院だけでも演習以外に7科目担当しました。最初に教えたのは、「企業財務論」という、ファイナンス全般をカバーする科目です。次に、夜間にファイナンスのサブコースができたのを機に「基礎ファイナンス」と「インベストメント理論」という科目を担当しました。その後も、受講生のニーズや、経営学研究科の組織的あるいは人的な変更に伴って授業内容を変え、科目名も変えてきました。直近では、経営学研究科での夜間コースの統廃合を契機に、昼間コースを充実しまして、私も昼間コースで「ファイナンス入門」を担当するようになりました。
経営学研究科でのご経験で何か印象に残った出来事はありますか。
2004年度に研究科長を務めましたが、その時に研究科独自のウェブページを作成しました。当時はインターネットの普及が進み、実施したアンケートでも受験希望者がネットで情報を収集している様子が明らかになりまして、研究科独自のホームページを作成しようという話になりました。当時副主任の筒井知彦先生と、法政に赴任して間もなかった入戸野健先生と児玉靖司先生がボランティアで協力くださって、教員手造りのホームページが出来上がりました。
より広く、法政大学でのご経験で印象に残っている出来事はありますか。
学部には全ての科目を英語で教授する、Global Business Program(GBP)が2016年度秋学期にスタートしましたが、その設立委員会のメンバーとしてカリキュラムの策定に関わりました。その際、グローバルスタンダードのビジネス教育が必要との思いが強くありました。議論を重ねた結果として、GBPでの入門科目の設定は、基本的にアメリカ型の教育を踏襲することになり、経営学の主要分野の入門科目を一年目の基礎科目として配置しました。
アメリカのビジネス教育についてもう少し詳しく教えてください。
アメリカのビジネス教育について散見される誤解を四点お話ししたいと思います。まず、日本でMBAというとビジネス系の大学院教育のことを指しますが、アメリカではカリキュラムについて特定の要件を満たしているものをMBA(Master of Business Administration)と呼びます。具体的には米国のMBAでは一年目にビジネス教育の主要科目を必修科目として履修し、二年目に専門科目を自由に選択して履修します。ビジネススクールによっては、特定の学問分野で一定数の単位を取れば、その分野を主専攻(major)にしたとMBAに併記できる制度を設けていることがあります。例えば、ファイナンスを主専攻にする場合は、ファイナンスの科目を一定数履修すればよいです。米国でMBAと略称される学位は、このような形で運営されているプログラムに入学してすべての要件を満たしたときに授与される学位です。
他方、大学によっては、特定の学問分野の科目を集中的に履修した者にその分野に関する修士号を授与するプログラムを開設しています。たとえば、複数の大学で Master of Science in Finance (MSc in Finance)を授与するプログラムが開設されていまして、そのプログラムに入学した学生は、ファイナンスとそれに関連する分野の科目しか勉強しません。ちなみに、日本のビジネススクールでは、主要科目の履修を必修化していませんので、日本のMBAはアメリカで言うMBAとは同じものではありません。
二点目として、アメリカのビジネススクールは、大学組織の中でかなりの独立性を持っているように感じました。したがって、日本の大学組織の中でアメリカのビジネススクールほど独立性が高い組織単位はないという印象をもっていますが、あえて挙げると「部局」が近いと思います。
三点目のポイントとして、ハーバードのように修士・博士のプログラムをオファーしているビジネススクールもありますが、NYUやウォートン(Wharton)のように大学院だけでなく学部のプログラムをオファーしているビジネススクールもあります。つまり、ビジネススクールイコール大学院ではありません。
最後に、アメリカのMBAにおけるビジネス教育は、基本的に、ビジネス教育を受けたことのない人が入学することを前提にしています。ですので、最初の基礎科目の授業内容は学部とほぼ同じでして教科書も同じものが使われる例が多いと思います。但し、大学院の場合は進度が早く、教える内容にレベルの高いものが含まれていることが多いのではないかと思います。
ご退職するにあたり、後輩教員へのメッセージをお願いできますか。
私はNYU、前々任校のデューク大学、デューク大学在任中に一学期間滞在したMIT(Massachusetts Institute Technology)、さらにボストン在住の際見学する機会を得たハーバード大学、前任校の筑波大学、そして法政大学と、多くの大学で授業見学をしました。法政大学だけでも10以上の科目の授業を見学しましたが、どの科目も面白かったです。内容自体が非常に興味深いものだった授業もありますが、それ以外にも最初は私語が教室の数か所で起こっていたのに授業が進むにつれ学生が役に立つ内容だと認識しているせいか、私語が自然にやんだ授業もありました。また、クイズを毎回実施する授業ですとか、質問を奨励して褒賞する制度をつくっている授業ですとか、どの授業でも独自の工夫が凝らされていました。私の授業でも、これらの工夫を参考にしました。ですので、同僚の皆さんには授業見学を強くお勧めします。
また、授業でアンケートを取ることもお勧めします。どのトピックが面白かったとか、どのトピックをもっと聞きたいかなど、担当する授業について、学生から様々な意見を聞くことができるからです。また、本学では大規模授業に授業アシスタントをつけることができますが、アシスタントにも毎回の授業についてコメントをもらっていました。小規模授業でもアンケートを毎学期やりました。アンケート結果は、私が予想した通りのこともありましたが、そうでないこともありましたので、やはりアンケートは参考になりました。私は、こうしたフィードバックに基づいて、授業内容や実施方法に工夫を凝らしてきました。
授業の実施方法としては、パワーポイントのスライドを配布すると同時に授業で投影しました。また、黒板いっぱいに板書することが多かったですし、黒板の右側に目次を提示しつつ講義を進めました。さらに、リアルタイムのデータを見せるために日経の電子版の相場表やそれ以外のネット上の情報をプロジェクターで投影したり、予め切り取った新聞記事を書画カメラ経由で投影したりと、様々な器具や手法を使って授業を進めました。
ちなみに、経営学部の教員にはご自身の専門分野以外の分野について馴染みがない方もいらっしゃると思います。ですので、各教員がご自分の分野を紹介する記事を同僚や学生向けに書き、紀要や大学のホームページに掲載することを検討されると良いと思います。
院生や志願者へのメッセージをお願いします。
経営学研究科で学んだ知識や技術を卒業のキャリアに生かすという観点から言えば、経営学の主要分野のそれぞれの入門科目を一通り勉強することをお勧めします。日本の企業ではキャリアが進むにつれて様々な職務に就くことがあると思いますが、どの知識が役に立つかは事前に分かりません。資本コストのことを知らなくてはいけない職務に就けばファイナンスの授業を取っていれば、商品開発にかかわる職務ならマーケティングの授業を取っていれば、財務諸表を読まないといけなくなれば会計を勉強しておけば、人間関係上の課題があればマネジメントを勉強していれば、となりますよね。もちろん大学院で勉強した知識や技術が卒業直後から即座に役に立つことはそれほどないかもしれませんが、一通り勉強していれば、必要性が生まれた時にある程度対応できますし,また,どの分野の書籍を参考にすればよいか、見当がつきますよね。経営学研究科には経営学やその関連領域について様々な科目が開講されているので、それらの科目のうち、主要分野の基礎的科目を一通り勉強することをお勧めします。
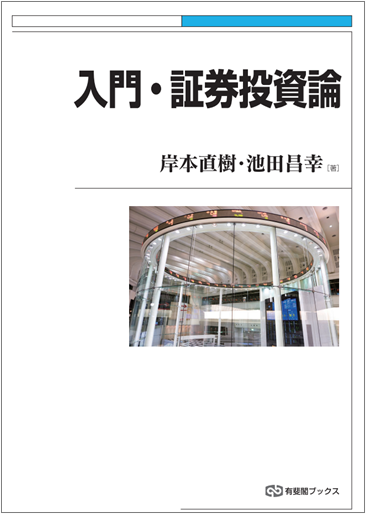
今後のご予定などお聞かせください。
日本の大学ではファイナンス系の教員はあまり多くなく、学部でも大学院でもアメリカのような標準的な科目が十分開講されている例は稀だと思います。ファイナンスという学問はアメリカで生まれ、発達したので、日本の著者がファイナンスの教科書を書く場合、アメリカの教科書を参考にしているだろうと想像します。ただし、アメリカの典型的な教科書は凡そ1000ページもありますので、各トピックに詳しい説明がなされ、事例や問題も多く含まれています。日本では教科書のページ数を増やすと価格が高くなるので、どうしても300ページくらいに収める必要があり、各トピックの説明をコンパクトにまとめざるを得なくなります。これは特に日本の入門レベルの教科書にみられる現象のように思います。そこで、私は、2019年に早稲田大学の池田昌幸先生と共に出版した『入門・証券投資論』で,説明するトピックを限定する代わりに、各トピックを通例より詳しく説明しました。退職後は、コーポレート・ファイナンスのトピックについて、とりあえず、同様の趣旨の教材を作って公開したいと考えています。
本日は、大変興味深いお話を聞かせていただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
きしもと なおき
法政大学経営学研究科 アカウンティング・ファイナンスコース
2001年4月~2025年3月
(2024年度研究科長 西川真規子によるインタビュー)