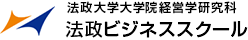HBSインタビュー

竹内淑恵先生
教員は院生の研究パートナー
法政大学大学院経営学研究科教授
2012年度・2013年度 経営学研究科長
竹内淑恵先生
研究を始めたきっかけについて教えてください。
研究室の片づけをしていて、忘れていた古い取材記事(マガジンハウス「社会人大学と通信教育の手引き 社会人ほど勉強したくなる」、『ダカーポ』No.310、1994年10月5日号)を偶然見つけました。その記事で、社会人院生になった30年前の私が、「当時勤めていた会社・ライオン㈱で研究職からマーケティング本部に異動したものの、広告作りもマーケティングも全くの初心者。無我夢中の時期が過ぎたころから、仕事を続けていく上での自分のベースとなるものが欲しくなってきた」ときっかけを述べています。
30年前というとまさに社会人大学院生の先駆けですね。ところで大学院はどちらへ行かれたのですか。
学部では家政学を専攻したので、早稲田大学の社会科学部に3年次に編入し直したり、短期のマーケティング講座に通ったりもしましたが、結局辿り着いたのは筑波大学大学院の経営システム科学専攻でした。先ほどの記事にも、筑波大学大学院で、「仕事上考えていたようなことを議論し、体系的に研究できることが本当に役立つ」、「ふと気が付くと仕事でのものの見方に学問的要素が重なることがある」とあります。
「MBAは誰にでも取れます」
修士課程の入学時(1994年)に会計の加古宜士先生からいただいた忘れられない言葉です。私もマーケティングコースの学生さんに「誤解を恐れずに言うと」という但し書きをつけて授業の際にお話しています。勿論寝ていてMBAを取れるわけではありませんが、ちゃんと取り組む限りは誰にでも取れる、という意味でお伝えしています。私自身も1996年3月に無事修士の学位を取得しました。丁度翌4月に博士課程の1期生の募集がありました。当時の指導教官の西尾チヅル先生からの勧めもあり、試験を受けてみました。
「博士はゴールではなく、スタートです」
それから博士の学位を取得するまでの3年間は結構大変だったという記憶があります。博士修了(1999年3月)の際、椿広計先生からいただいたこの言葉がとても印象に残っています。「博士の学位は独り立ちして良いということであって、これで終わりということではない。これをもってスタートしてしっかり研究せねば」と心に誓ったことを覚えています。とはいえ、相変わらず、ライオンで仕事をしていたので、なかなか研究をできる環境にはなく、忸怩たる思いで過ごしていました。
会社勤めから大学教員に転身されたわけですよね。教育に携わるようになったきっかけ、法政に来られた経緯を教えてください。
会社には定年まで勤めるつもりだったのですが、指導教官の西尾先生から、「会社勤めだと女性ならではのガラスの天井もある。大学教員は教育にも携わらなければならないが、研究する時間も取れるので選択肢の一つでは?」とアドバイスをいただきました。それまでそのようなことを考えたこともなく、大学で教えた経験もなかったので、まずは教歴をつけるべく、どこかで非常勤講師を、という話になりました。そこで、博士の学位を取得した翌月から学習院や理科大の他、法政の経済学部(当時の二部)の夜間の授業を非常勤で受け持つことにしました。その後、社会科学研究科(現・経営学研究科)の客員教員を経て、2003年4月に経営学部の専任教員として採用されました。
当時の経営学部や経営学研究科の様子は覚えていますか。
採用された側ですから、当時の経営学部や経営学研究科のことはよくわかっていませんが、学部が3学科制になったことで教員数の枠が増えて採用いただいたようです。学部ではマーケティング論を小川孔輔先生とダブルキャストで担当しました。その他にインターンシップも担当しましたが、かなり大変だったという記憶があります。
22年も前から学部でインターンシップを実施されていたのですか。
当時の科目名は、マーケティング実務とマーケティング研修、それぞれ2単位科目でした。前半のマーケティング実務では、毎回ゲストスピーカーを招いて企業の経営やマーケティングのお話を、後半のマーケティング研修では、前半で講義を受けた企業で夏季休暇中1~2週間の実習を受けるというカリキュラムです。実習への協力企業を探すのが大変で、他の先生やHBSの大学院生に協力いただいたりもしました。夏休みの研修の際には、学生の様子を確認しに企業への挨拶周りもしました。一人で回りきらず、途中から委員会にしていただいて2,3名の先生で手分けして挨拶周りに伺ったものです。ちなみに学部生のインターンシップは今では当たり前となりましたが、経営学部では1996年からインターンシップを正規科目として実施していましたので、私立大学では先駆けだと思います。
着任当時の大学院の様子は覚えておられますか。
大学院に関しては、ちょうどイノベーション・マネジメント研究科が設立された頃で、マーケティングコースから小川孔輔先生、矢作敏行先生の2名が移籍された他、田中洋先生もアメリカでの在外研究に出かけられるなど、看板教授が3名もいらっしゃらない状況の中でのスタートでした。多少なりとも大学院の授業を持った経験はあったにせよ、専任歴1年目の私がいきなりマーケティング論の授業を担当し、修士論文も3名指導。今考えるとよく務まったものだと思います。
マーケティングの中でのご専門領域について分かり易く教えてください。
そもそもの研究の始まりは、毎日試験管をふっているような研究員からマーケティングの部署に異動となり、右も左もわからないまま広告制作というクリエイティブな仕事に無我夢中で携わるうち、自分が担当しているブランドのテレビ広告の効果を解明したい、という問題意識でした。そこから現在まで一貫して、『マーケティング・コミュニケーション効果の検証』が研究テーマとなっています。私が研究を始める入り口となったテレビ広告に限らず、企業が発信するコミュニケーション手段には、新聞、雑誌、ラジオなどいわゆるマスコミ媒体の他、意外に思われるかもしれませんが、製品パッケージも店頭において最終的に購買を後押しする重要なコミュニケーション・ツールとなっています。製品パッケージ上での情報の伝え方の巧拙によって、消費者の背中を押す力が異なるので、その効果検証も必要です。さらに、近ごろのSNSの台頭により、企業もSNSを積極的に活用して消費者とコンタクトを取っています。そのやり方次第で、効果が認められたり、逆に炎上したり、という可能性もあるわけです。
研究テーマはどのように変わりましたか。
スタートは『広告コミュケーション効果の検証』でしたが、その後研究対象を拡張し、『マーケティング・コミュニケーション効果』をテーマとして研究に取り組んできました。このテーマには、消費者行動論、ブランド論も関連します。企業側が発信する情報を受け取るのは消費者ですから、受け手である消費者の行動を理解する必要があります。そして、1990年台前半から脚光を浴びてきたブランド論(注:アメリカにおいて多くの企業が短期的な成果を追い求めていることに対して警鐘を鳴らし、長期的な視点でブランドを育成すべきという論点)の中での、広告はブランドの育成に役立つ、という主張に私は背中を押された感じがしました。私の修士論文や博士論文もこの主張に則っています。ブランドを育てるのは一朝一夕ではできません。だから、長期的な累積効果を検討する必要がある、ということで、ブランド論も対象領域としています。
社会人の研究指導について教えてください。社会人が論文を書くことにはどういった意義があるのでしょうか。
経営学研究科の特徴はアカデミックな修士論文を書くことが必修科目になっており、この点において他の大学院、特に専門職大学院とは一線を画します。私自身も社会人大学院の経験者であり、修士論文も書きましたので、経営学研究科のカリキュラムはとても魅力的だと思っています。社会人として、実務での問題意識に根差した研究論題を設定し、その解明に向けて研究を進めてまとめていくわけです。理論や分析のノウハウなどは確かに教員のほうが優れていますが、課題の設定は、実務家であり切実感をもって課題解決に取り組もうとしている院生自身の観点が重要です。そこで必要なのは、教える教わるという上下関係ではありません。
上下関係ではない、とすれば、どのような関係でしょうか。
私自身は指導教員を院生の『研究パートナー』だと考えています。時にはコーチのように方向付けをしつつも、ある種対等な立場で、パートナーとして問題を共有し、議論を重ねて取り組む必要があります。とはいえ、院生の修論執筆に対しては、かなり詳細に校閲を行いました。初校は赤字だらけで返却、3回くらいはチェックしやり取りをする、というのが毎年の恒例です。年明け早々の提出なので年末年始もありません。ゼミ生にとっては初めて書く論文です。実務の報告書やプレゼン資料とは違う作法で書かなければならないので、かなり厳しかったのではないかと思います。ですが、こうして最終的に論文としてまとめることで完成度の高い修論が出来上がると考えています。院生には、積極的に学会発表を推奨してきたので、実際に修士論文を学会で発表したケースも多かったです。一般的には修士論文は業績カウントしないなどと言われていますが、社会人大学院生が取り組むテーマは実務の課題に対して正面から取り組んでいて、発表するに値する価値あるテーマだと考えています。
HBSで担当された授業について教えてください。
着任当初はコトラーのマーケティング・マネジメント論の原著を使っていました。ですが、授業評価アンケートの結果を見ると不評で、英語の翻訳で一杯いっぱいだ、そもそもマーケティングの基礎がわかっていないのでそれを講義してほしい、英語の勉強をしにきたわけじゃない、といった声が散見されました。英語版を用いたのは前任者からの引き継ぎでしたが、私自身もマーケティングコースの基本的な科目を任されているという気負いがあったのかもしれません。そういうことなら日本語版にしましょう、ということで変更し、さらに、2限続きの2コマ目は、受講生みんなで議論する時間に変更しました。90分(今は100分)も議論できるのか、持たないのじゃないかと当初は懸念していましたが、実務経験者としていろいろな課題を抱え、問題意識も持っており、当然のことながら自社のケースを話すことになるわけで、話は尽きることがないということで杞憂に終わりました。去年と今年は受講生も比較的少なかったので、新刊の本を輪読して、議論の時間に充てようという形で実施しました。定番の教科書とは別に、新しい本を読んで議論できて、結果的には良かったと思います。大学院の授業は受講生のニーズに合わせて比較的臨機応変にできる点が良いと感じています。
マーケティングコースではワークショップも開催されていますね。
経営学研究科の特徴であるワークショップの授業は、マーケティングコースの場合、実務家を客員教授として招聘することが多いです。私が知る限りにおいても、歴代、冨狭泰先生、竹中雄三先生、小林健一先生、朝岡崇史先生などいろいろな先生にお世話になっています。実務家であるがゆえに、多方面からゲストスピーカーをお招きし、受講生からも好評を得ていますが、我々教員も時には授業に参加して、外部の方のお話を伺う良い機会にもなっています。授業後に皆でお昼を食べに行き、さらに議論が深まったこともありました。
HBSで印象に残っている出来事は何でしょうか。
学部ゼミの3期生の片山貴仁さんが社会人になってからHBSに入学し、修論指導ができたことです。学部の卒業(2006年度)から大学院の修了(2016年度)までちょうど10年経っていました。これからも学部を卒業した後にHBSに戻ってきてくれる人が増えてほしいと思っています。私自身がそうだったように、ある程度実務の経験を積んで、その中で疑問に思ったり、解決したりしたい課題が出てきたら、実務的な側面だけでなく、理論的な角度から検討してみると良いのではないかと思います。学部卒業生の皆さん、ぜひ、HBSの扉を叩いてみてください。
 片山貴仁氏との10年前(2007年3月24日・左)と10年後(2017年3月24日・右)
片山貴仁氏との10年前(2007年3月24日・左)と10年後(2017年3月24日・右)
その他に印象に残っている出来事はありますか。
同じ年に論文指導を担当した中国からの留学生も印象に残っています。日本語より英語のほうが得意で、英語で書かれた先行研究をよく読み、独自の視点で研究に臨む姿勢が真摯で、とても好感を持ちました。研究素材としてテレビCMを選ぶ必要があったのですが、1日中家から出ずに、テレビを見通しだったと聞いてびっくりしたことを覚えています。初めての分析にも、マンツーマンの厳しい指導に粘り強く取り組んでいました。この年は先ほどの片山さんの他、博士課程の院生も2名受け持っていましたが、これら同級生、先輩からいろいろと教えてもらったりもして心強かっただろうと思います。修了後は帰国し、日本語通訳としての就職も決まり、学生時代からの交際相手と結婚したと聞きました。幸せそうな結婚写真と共に送られたメッセージには「ゼミの皆さんとまた会いたい」とありました。修了後にもこのようにコンタクトを持てたのは、法政大学大学院での日々がとても楽しくて充実していた証だと思います。社会人修士と、留学生、さらに社会人博士も交えてゼミを行うとシナジー効果が発揮される気がします。
授業にはどのような工夫をしてきましたか。
2020年のコロナ禍以降授業のやり方が変わりました。当時はやむを得ずオンラインでのゼミとなりましたが、良い面もありました。博士号取得後、研究者や大学教員として活躍したり、修士号取得後大学教員になったりした先輩(剣持真さん、渋瀬雅彦さん、三浦卓己さん)がゼミに参加してくださったのです。修士2年目の前半は、先行研究のレビューや仮説設定など、重要な研究の枠組みを決める大事な時期です。その際これら先輩たちからのアドバイスをもらい、十分に議論する機会を設けることができたのはとても良かったです。私にとっても、先輩たちの意見を聞けるのは大変ありがたかったですし、先輩たちにとっても、後輩の研究にサジェスチョンできる機会があるのは勉強になったことと思います。ですから、コロナが5類に移行した後もこのようなゼミのやり方を踏襲しています。
院生との交流について、さらに教えていただけますか。
2020年度は博士2名、修士2名が無事修了し、思い出に残る年でした。博士の内1名は博士8年+修士2年、なんと計10年間在籍、もう1名は3年で学位を取得されましたので対照的でした。博士の学位は田中優子総長(当時)が直々に一人ひとり授与されるため、私も武道館の式典に馳せ参じました。博士の取得はある種いばらの道ですから、博士を送り出すという責任が果たせてホッとしたことを覚えています。
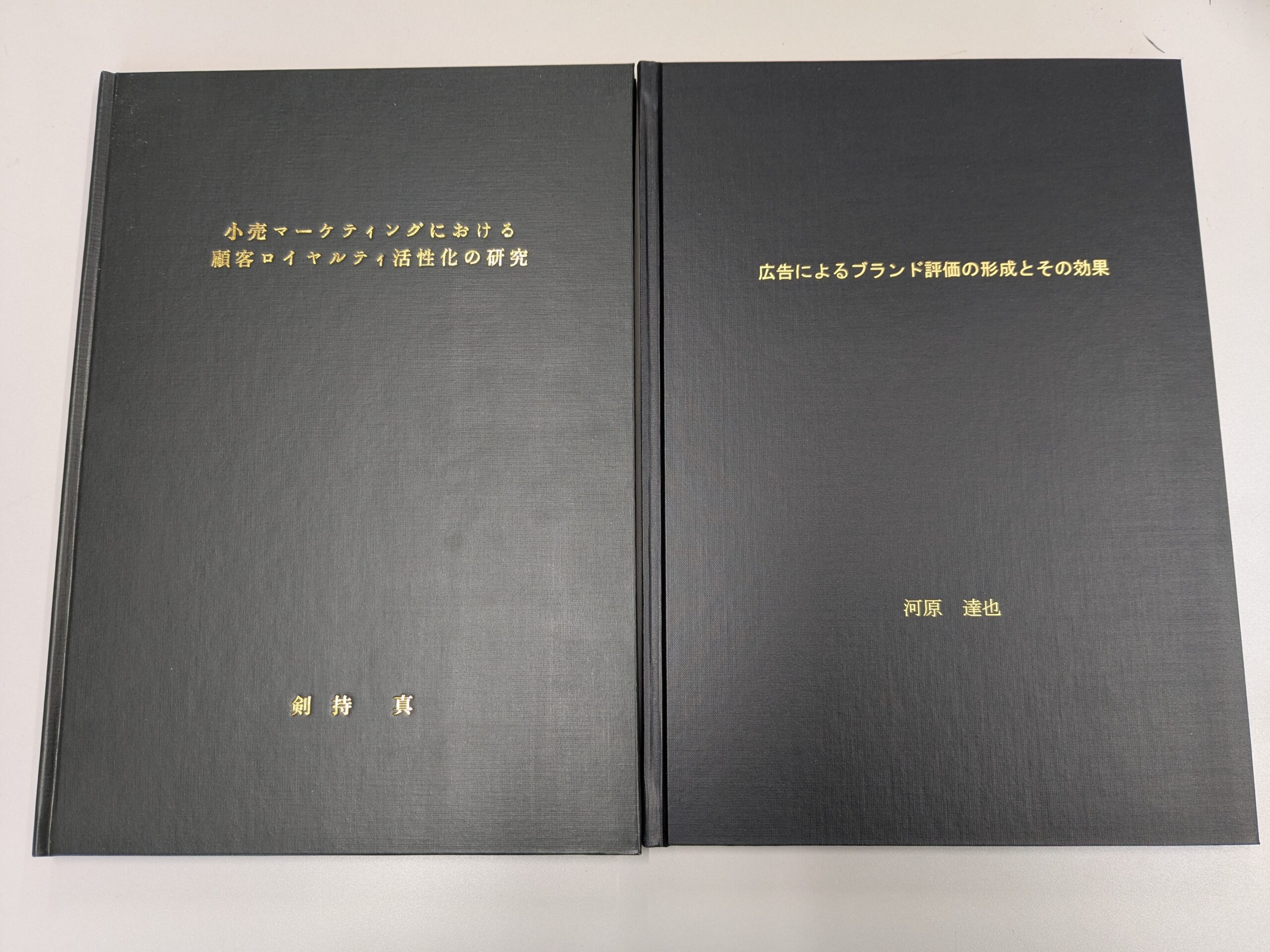 左:2017年度剣持真氏博士論文、右:2020年度河原達也氏博士論文
左:2017年度剣持真氏博士論文、右:2020年度河原達也氏博士論文
 2021年3月24日日本武道館にて
2021年3月24日日本武道館にて
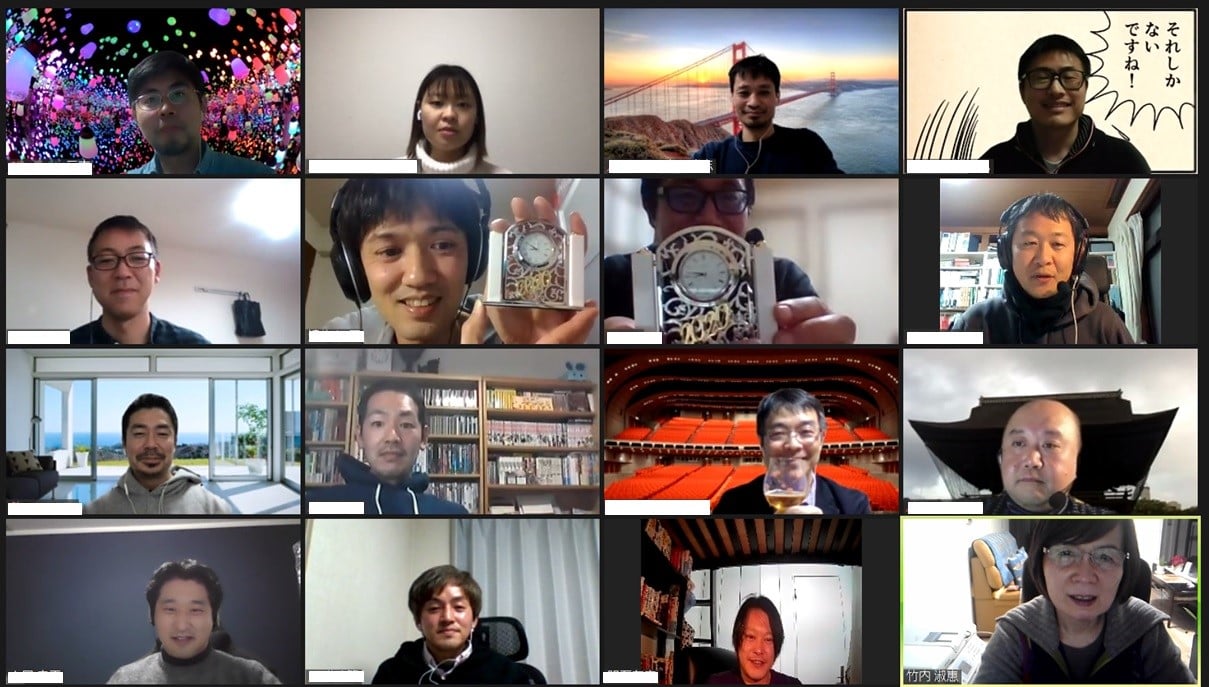 Zoomで開催した博士取得のお祝い会
Zoomで開催した博士取得のお祝い会
修士修了生からは後日、お子さんと一緒に撮った写真と共に次のようなコメントが送られてきました。
この2年間、私が何をしてきたかもよく分からない子どもたちですが、きっと親の背中を見ていないようで見ているものだと思いますので、自分が努力して苦労して達成して、そして喜んでいるといった姿を見せれたことは、将来、良い影響を与えてくれるものと信じています。
ご家族の理解あっての大学院進学だとは思いますが、長い人生から考えればたった2年間、そう思えば短いものです。M2のときにお子さんが生まれた男性の院生は、夜間ぐずっている赤ちゃんをだっこしながら、論文を執筆したそうです。
 2021年3月27日嵯峨篤氏「桜咲く」
2021年3月27日嵯峨篤氏「桜咲く」
最近は、通信教育課程からHBSへ進学する人も増えていますね。
通信教育課程では、マーケティング論Ⅰ・Ⅱと広告論の3科目を、2013年から12年間メディアスクーリングにて開講していますが、その中から、HBSに進学してくださった方もおられます。これも大変嬉しいことです。通教には多様な経歴の方がいらっしゃいますが、より深く勉強したいと考えている方が多いので、マーケティングコースに限らず、もっと受け入れていきたいものだと思います。先日、レポートの採点をしていたら、ある方がレポートの最後に以下のようなメッセージを書いてくださっていました。
マーケティング論ⅠとⅡ、さらに広告論も履修しました。コンプリートです。そして、経営学研究科への進学も検討しています。
こういうメッセージを読むと、何百枚もあるレポート採点の苦労も一気に吹き飛びます。
より広く法政大学でのご経験で印象に残っている出来事は何ですか。
22年間在職していたので、いろいろと思い出話はあるのですが、特に印象に残ったことを2点お話します。
『グローバルビジネスプログラム(GBP)』
学部長1年目の秋(2014年9月)にSGU(スーパーグローバル大学)に法政が採択され、英語で授業を行い、学位が取れるコースを作るということになりました。経営学部でもGBPを設立することになりました。ゼロからの立ち上げですから、教授会でも議論に議論を重ね、相当時間をかけて検討しましたが、実に大変でした。学部長在職中に入学試験を実施し、次期学部長の奥西好夫先生にバトンタッチして、2016年秋学期からスタートしました。GBPは始めてからもう8年も経つのだと思うと、隔世の感があります。
『赤坂優奨学金』
学部長2年目の最後の日、2016年3月31日のことです。ある委員会で奨学金の話が出たので、ふと思いついて、この奨学金設立の橋渡しをしました。赤坂優さんは学部ゼミの2期生で、2006年3月に卒業し、2008年にエウレカ(マッチングアプリのペアーズの会社)を起業しました。そのビジネスが成功をおさめて、2015年に全株式を米国IACグループ傘下のThe Match Groupに売却したことで話題になりました。なんと当時の額としては破格の3桁億100億円越えとのこと、そこで私は赤坂さんに「そんなに儲かったのだったら、後輩たちのために冠奨学金をやってくれない?」と話を持ち掛けました。そうしたら、あっさりOKの返事をくださって、毎年2名×25万円の枠で10年間、返済なしの経営学部生向け奨学金制度を設立してくださいました。その後、彼はエウレカを後進に譲り、別の会社を設立しましたが、今でも日本のスタートアップを中心に約90社に出資するエンジェル投資家としても活躍しています。
 赤坂優氏との10年前(2006年3月・左)と10年後(2016年10月・右 田路先生も参加)
赤坂優氏との10年前(2006年3月・左)と10年後(2016年10月・右 田路先生も参加)
最後に院生や志願者へのメッセージをお願いできますか。
最初に修士の方へのメッセージです。
先行研究をしっかり調べる
ここで大事なのは、先行研究の結果をそのまま受け入れるのではなく、批判的に読むということです。先人たちはそれぞれが自分の研究目的や仮説の下に研究しているわけで、その成果が認められて学会誌に掲載されているので、そういう点で大いに参考にして受け入れるべきですが、一方で、自分が取り組もうと考えているテーマに照らし合わせたとき、先人たちとは違った視点で「ちょっと違うのではないか、ここが、自分が考えていることや実務の経験から見て違和感がある」といった批判が生まれてくるはずです。先行研究の追試をしても論文としての価値はありませんから、研究のオリジナリティを十分に意識して、仮説を設定し、検証すべきだと思います。
統計学、データ分析を十分に理解する
検証に際しては、統計的データ解析がツールとなります。Rなどのソフトウェアを用いればアウトプットがすぐに出てしまうのですが、これで終わりということはありません。その手法でなにがわかるのか、出てきた数値にどのような意味があるのか、それをわかったうえで用いる必要があります。ですから、少なくとも定量的な分析を行うことを予定しているのであれば、修士1年のときに統計学などの授業をきちんと履修しておくことが必要です。
スケジュール管理をしっかり行う
会社員時代に上司に言われた言葉で「納期の厳守、お金(予算)とスケジュール管理が大事」という言葉が記憶に残っています。修士論文に取り組むに際しても、提出締切である納期を厳守するために、途中経過としてのスケジュール管理をしっかりしてください。なにかあったときに対応するためにも早め早めに進めておくことが重要です。だいたい予定というのは遅れるものですから、早くやっておくに越したことはないということです。
研究助成にチャレンジする
研究を進める中で、定量的なアプローチの場合、調査を実施することが多いと思います。その場合にはそれなりに費用がかかるので、修士と博士の方に共通することとして、自分の研究分野で研究助成が行われているのであれば、それにチャレンジすることをお勧めします。
 石井俊宏氏 2004年11月9日第2回助成研究論文吉田秀雄賞授賞式
石井俊宏氏 2004年11月9日第2回助成研究論文吉田秀雄賞授賞式
上は大学院ゼミ1期生のかたが、公益財団法人・吉田秀雄記念事業財団の研究助成の大学院生の部で研究費を補助していただき、その成果である論文が第1席の賞をいただいたときの写真です。最近では、2023年3月に修了した荻野茂男さんが日本プロモーショナル・マーケティング学会で研究助成をいただき、その成果が査読論文として掲載されるとともに、2023年度研究助成論文「学会賞」を受賞しました。URLを掲載しますので、ご一読いただけると幸いです。
本学修了生の論文が日本プロモーショナル・マーケティング学会誌に掲載されました – 法政ビジネススクール(法政大学大学院経営学研究科)
本学修了生の論文が日本プロモーショナル・マーケティング学会誌の学会賞を受賞しました – 法政ビジネススクール(法政大学大学院経営学研究科)
次に博士の方へのメッセージです。
ステップ制を活用したスケジュール管理と着実な業績づくり
ステップ制度を意識して、スケジュール管理をしっかりすることが重要です。焦る必要は勿論なく、十分検討した上で成果を出す必要はありますが、早く学位は取りたいものですよね。そうであれば、ステップを1つずつ着実にクリアしていくこと、業績をしっかり作っていくことも大事です。そのためにも博士課程1年の最初に研究計画書をしっかり書いておくこと。1つの研究テーマに対して、例えば、定量的アプローチであれば、第1章の「はじめに」、第2章の「先行研究のレビュー」の後に続く、3本の実証研究が必要です。この3本の枠組みを作っておくと、道標がしっかりして研究を進めやすいと思います。そして、その3本を1つずつ論文としてまとめ、査読ジャーナルに投稿を行うことです(博士論文では最低1本の査読論文が必要)。査読にはそれなりに時間がかかりますから、そのあたりも念頭に置いて、粛々と研究を進めると良いと思います。
最後に志願者へのメッセージです。
MBAは誰にでも取れる
最初にお話した通り、誤解を恐れずに言うと、MBAは誰にでも取れますので、ぜひチャレンジしてください。リカレント教育とか、リスキリングといったことが話題になっていますが、少しでもご興味があるなら、そして、ためらっているなら、やってみる価値があるよとお勧めします。ある人が「HBSに入ったら、ジェットコースターに乗ったみたいだった」と言っていました。その心は、山あり、谷あり、怖いけど乗ったら最後降りられない、ということですが、ご本人はジェットコースターを十分に楽しんだようです。年に何度か進学相談会やセミナーも開催していますから、ぜひそういった機会を活用されると良いと思います。研究計画書の書き方とか受験の心構えとか、時間割の組み方とか、そういった質問も個別相談の機会に伺ってみるのも一つの方法だと思います。
この度は楽しく為になるお話を沢山聞かせてくださりありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。HBSがますます発展することを祈念しております。
たけうち としえ
法政大学経営学研究科 マーケティングコース
2003年4月~2025年3月
(2024年度研究科長 西川真規子によるインタビュー)