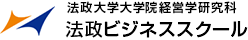HBSインタビュー

法政ビジネススクールの33年
法政大学大学院経営学研究科教授
1997年度、1998年度経営学専攻副主任
大下勇二先生
法政大学大学院経営学研究科教授
1998年度経営学専攻主任
2007年度~2009年度 経営学研究科長
横内正雄先生
 横内正雄先生(左)大下勇二先生(右)
横内正雄先生(左)大下勇二先生(右)
大下先生、研究をはじめたきっかっけ、研究者になった経緯を教えてください。
【大下】 神戸商科大学での学部生の時、会計士になろうと試験勉強をしていました。兄が会計士で監査法人に勤めており、面白そうだなと思ったんですね。ですが、試験勉強を続けるうちに、計算問題を解くよりも、自分にはじっくり考える方が向いていると思うようになり、大学院に進学することにしました。研究者になるつもりはなかったのですが、大学院の指導教官がとても個性的な方で、ヨーロッパ、中でもフランスの研究をなさっており、私も学部時代にフランス語の授業をとっていたこともあって、フランスの研究をすることになりました。大学院ではフランス語の原書をずっと読むような毎日を送っていましたが、博士課程2年目の秋に法政大学の研究助手の公募があったんです。私は高松出身ですし、関西には沢山大学もありますから、東京で就職するつもりはなかったのですが、指導教官に勧められたこともあり、受験したら受かってしまいました。ちょうど博士課程2年目が終わった頃で、中退するのかなと思っていたら、在籍したまま助手に採用してくれるとのこと。当時の助手は博士課程を修了してから2年間が決まりだったので、私の場合、博士課程3年目とその後2年を加えて、結局3年間助手をしました。当時の助手は研究だけをしていればよかったので大変恵まれていましたね。
その頃の法政大学の様子を教えてくださいますか。
【大下】1983年4月に着任しましたが、その頃法政大学は多摩への移転問題(*市ヶ谷キャンパスから多摩キャンパスへの全学移転を計画)で大揺れに揺れた後でした。当時、理事会は全面移転を主張していたようでしたが、経営学部は岡田裕之学部長(当時)の下で市ヶ谷に残ると反対したんですね。大学内は賛成派と反対派で二分されていましたが、結局、経済学部と社会学部だけが多摩キャンパスに移転、経営学部も含めた他学部は市ヶ谷キャンパスに残ることになりました。私はこの問題が一件落着した後に着任したので、少し落ち着きが戻ってきたような感じだったと思います。
経営学部の様子はどうでしたか。
【大下】当時の経営学部にはまだ創設者メンバーがかなり残っておられました。経営学部は経済学部から分離独立しましたので(*分離独立は1959年)、当時は産業経済分野の先生が非常に多かったですね。創設時の学部長は、傾斜生産方式の立案者である有沢広巳先生でした。経営学部とはいいながら、産業経済分野の研究者が多く、独立後しばらくは産業経済分野に強い経営学部というのが売りだったようです。2003年4月からの3学科体制に移行するまでは、1学科・3系列体制(経営系列、会計系列、産業・経済系列)をとっておりました。
【横内】この3系列は実は今でも大学院の入試の出題の分類に残っています。
その後の経営学部について教えてください。
【大下】助手の後、専任講師、助教授(*現在の准教授)となり、1988年10月から1990年3月まで教授会副主任を務めました。当時の副主任の仕事は主に学生問題への対応でしたが、本当に大変でした。当時、学生会館(*今は取り壊し)という建物の中に学生の自治会があったんです。大学が学生の自治会費を代理徴収していたのですが、この自治会との交渉を主に担当していたのが、副主任だったんですね。
【横内】当時の外国語経営学は学部の必修科目でしたから、クラス分けされたそれぞれの教室へ自治会の学生が来て、選挙と称して各クラスから代議員を選びに来ていましたね。自治会には、副主任と二人の学生生活委員と3人で対応していました。
【大下】それから、この頃の市ヶ谷キャンパスには教養部があり、この教養部が1・2年生の教養課程を担当し、経営学部を含めた専門学部が3・4年生の専門課程を担当していました。その後、教養部は解消し、教員は専門学部に分属になりました。
【横内】分属後の教養教育の組織が今のILACですね。
【大下】いろいろあったものの、80年代はちょっと落ち着いた感じの時代でしたね。
その頃の大学院の様子についても教えていただけますか。
【大下】大学院の初めは、社会科学研究科の経済学専攻でした。当時、会計分野で有名な先生が立派な本をだされて、法政大学で博士号を取りたいという話があって、経営学部の会計の先生が窓口になったんですね。それで多摩キャンパスの経済学部の教授会と電話であっちとこっちをつないで採決を取ったという記憶があります。今ならZoomでしょうが、当時は電話でした。まだボワソナードタワーができる前でしたから、その敷地に以前にあった大学院棟の会議室から電話を繋いだように記憶しています。
経済学専攻から経営学専攻が分離した形になったのでしょうか。
【大下】1992年に経営学専攻が昼夜開講制で発足しました。昼間コースと夜間コースを同時に創設しましたが、それまでは経済学専攻だったんです。
【横内】初め、夜間コースは、企業家養成コース、人的資源管理コース、マーケティングコース、経理人コースの4コース体制で,40人程学生がいましたね。昼間の学生も10人程いたように記憶しています。
【大下】夜間コースの方が人数は多いですが、実はメインは昼間のコースなんです。1階部分が昼間のコースで、2階部分に大きな夜間コースが設置されているイメージです。
【横内】昼間コースの延長として夜間コースがあるという立ち位置ですよね。
法政ビジネススクール設立の経緯について教えてください。
【大下】産業情報センターが1986年にスタートしましたが、その後にビジネススクールをつくるという一連のプランがあったようです。産業界とのパイプを強くするという狙いで、何人かの先生が中心となり計画をすすめられたようです。
【横内】1992年の発足時に、企業家養成コースを担当していたのは、清成忠男先生、宇田川勝先生、吉田健二先生ですね。経理人コースが、佐藤康男先生、坂口康先生、永野則雄先生。マーケティングコースは、小川孔輔先生、下川浩一先生、矢作敏行先生。人的資源管理コースは小池和夫先生、川喜多喬先生、佐藤博樹先生、とそれぞれのコースを3人くらいの教員で担当していました。
当時の夜間コースはどのような様子でしたか。
【横内】各コース十数人の学生がいましたが、経営学部の教員が全員夜間コースを受け持っていたわけではなかったので、一人あたり3,4人の修論指導を担当していました。ここにその頃の1994年度の資料がありますが、夜間4コースで合格者が44人とあります。
【大下】大学院の修士論文の指導をできる教員を増やしてほしいという声が強く出て、そういう即戦力となる教員を学部でも採用していく方向に変わっていきましたよね。こういう流れの中で、私の時のように若い研究助手を採用して育てることもなくなっていきました。
【横内】研究助手として採用となった最後は、洞口治夫先生と筒井知彦先生でしょうね。
【大下】経営学専攻が出来てから、ビジネススクールで指導できる教員、経営関連の人事が増え、ずいぶん変わりましたね。学部も三学科体制となり、経営関連の教員や科目が随分増えました。
【横内】院生も当時随分多かったですね。1998年度で合格者は74名、受験者は97年に154名、98年は159名とあります。
当時、ビジネススクールは珍しかったのでしょうか。
【大下】経営学専攻はビジネススクールのトップランナーのような感じでしたね。夜間コースのワークショップが特に当時は珍しく特色となっていました。ワークショップでは、産業界から人を読んで話をしてもらいますが、産業界とのパイプをつくるという考えがあったんでしょう。
【横内】経理人コースの最初のワークショップの様子は、本として出版されています(佐藤康男編『ケース・スタディ/日本型管理会計システム』中央経済社、1993年)。ここには大学院の設立の経緯も書かれていて、日本型ビジネススクールという言葉を使って説明しています。その後もビジネススクールの人気は続きました。2000年には165人、2002年には171人もの応募がありました。試験の時は大変でした。面接も夜8時ごろまでかかったことを覚えています。院生が一つのコースに20人くらいはいましたから、それは活気がありました。人的資源管理コースでは、夏には泊まり込みの合宿も実施したりしていたようです。
【大下】当時は入試に企業推薦制度もありました。志願者で会社の社長が自分で自分の推薦書を書いてきたりして大笑いしたこともあります。
【横内】博士課程で博士号取得者が最近増えていますが、私が専攻主任で大下先生が副主任だった1998年度にも博士号取得者が居ましたし、その後もコンスタントに博士号取得者が出ています。
【大下】博士課程の夜間コースを1990年代に設けていたことは珍しく(*日本初)、法政の経営学専攻のユニークな特徴としてあげられます。当時の経営学専攻では他にないものを次々にやっていた印象があります。
【横内】その後もコンスタントに博士号は出ているようですね。社会人で博士号を取って教員になった人も少なくないようですし。
横内先生は、経営学専攻が出来た年に法政に移ってこられたのですね。どのような経緯で法政へこられたのでしょうか。
【横内】私は大下先生と同様に、研究者になろうと思って大学の教員になったわけではなくて、最初は高校の世界史の先生になりたかったんです。長野県の信州大学の学部生終了時に、世界史の教員試験を受けたのですが、当時県内で3,4人しか採用されず、残念ながら受からなかったんです。その後も教員試験に挑戦しようと、大学院で研究生をしながら受験勉強をしていましたが、時間に余裕ができた時に横浜国立大学の大学院を受験してみたら合格したんです。当時は大学院を出ると高校の教員免許1級が取れたので、結局大学院に進学することにしました。横浜国立大学の大学院では、経済史の先生の下で2年研究しました。その後、東京大学の博士課程の試験を受けて合格し、東京大学経済学研究科に3年次から編入しました。今は知りませんが、当時の東京大学の大学院は第二種博士課程と言って修士課程と博士課程が連続していて、博士課程に編入するということで3年次に編入することになりました。その時に初めて研究者になろうと思ったんです。博士課程修了後、東北大学の助手に採用され、2年後に新潟大学の商業短期大学部へ移って、7年間夜間に社会人を相手に講義を担当しました。その後、銀行の歴史を研究されている法政大学の西村閑也先生とのご縁もあって、法政へ移ってきました。
法政赴任時は大学院とどう関わっておられましたか。
【横内】最初は、大学院の昼間のコースで国際銀行論を担当し、学生を指導していました。その後1995年に、国際経営コースを立ち上げる話が持ち上がり、そのプランを考えることになりました。考えついたのが、夜間各コースの国際版という案で、例えば国際マーケティング、国際会計、国際人事、国際経営等の科目でカリキュラムを構成しようということになったんです。その時は小林清人先生と私と二人だけでしたが、そこに在外研究中の洞口治夫先生も加わり、3人体制で96年度から国際経営コースが開始しました。開講直前ギリギリの3月に初めての入試を実施しましたが、開始年度には7名の合格者を出しました。
大学院の夜間コースは国際経営を入れて1996年に5コース体制となったのですね。
【横内】1995年の改革時には、国際経営コースの他、ベンチャーキャピタリスト養成というサブコースを企業家養成コースの中につくるという話もあり、講義科目も増やしたんです。
【大下】私は専門が会計ですから、最初は経理人コースを担当していましたが、この流れの中で、企業家養成コースに移ることになり、ベンチャービジネス監査論を担当することになりました。96年から論文指導も企業家養成コースで7年くらい担当しました。企業家養成コースでは、修士論文でなくビジネスプランの作成でも卒業できますが、その第一号は私が指導した学生だったんです。その後、私は経理人コースに戻り、さらにその後専門職大学院のアカウンティングスクールが2005年にできた時には二重籍教員になったりもしました。
【横内】専門職大学院といえば、最初にイノベーション・マネジメント研究科が2004年に開設されました。この頃には、他の大学でもビジネススクールが出来たりしていましたので、夜間のビジネスクールも珍しくなくなり、経営学専攻の志願者がぐっと減ったように思います。
【大下】1990年代と2000年代のビジネスクールは性格が少し変わってきたように思います。経営学専攻も専門職大学院との差別化を図るためにも、修士論文研究が中心となってきたように思います。
【横内】1990年代までは、経営学専攻はとても人気があったんですが。毎年ビジネススクールを特集する雑誌のランキングで社会人大学院の一位になったこともあったんですよ。あの頃、多摩大学とか慶応大学とか、社会人向けのビジネススクールがある大学同士の交流もあって、一緒に説明会を開催したりもしていました。ですが、専門職大学院が増えてからそういう交流もなくなりました。
大学院でのご経験で他に印象に残っていることはありますか。
【大下】1990年代は大学院の教授会が、学部の教授会の最後に専攻主任が立って10分くらい説明して終わり、というような感じでした。
【横内】当時会議室が80年館(*現在の図書館棟)の7階にあって、学部の教授会が終わると学部長が、「大学院は何かありますか」という感じで、経営学の専攻主任が「ちょっとだけ読み上げてよろしいでしょうか」という感じでしたね。当時はまだ経営学研究科ではなく、社会科学研究科の中の経営学専攻でしたから。
【大下】2004年になって社会科学研究科の中の各専攻が改組され、経営学専攻も研究科として独立したんです。
【横内】経営学研究科とはなったけれども、キャリアデザイン学専攻とも2005年以降しばらく一緒でした。だから4月の研究科教授会は、経営学専攻とキャリアデザイン学専攻が一緒に研究科教授会をやっていました。キャリアデザイン学専攻がその後2013年に独立した時に、経営学専攻イコール経営学研究科となったわけです。
その他に何か印象に残っていることはありますか。
【大下】印象に残っているといえば、コロナショックでしょうか。2020年の4月、授業が始まる前に、コロナで大変な時にどうやって授業をやるんだろうと思っていたんです。その時、田中優子総長(当時)がテレビ番組で「法政はもう準備はできています」とおっしゃいましたが、どうやるんだろうと本当に心配しました。
【横内】教授会も対面で開けず、情報共有もままならない中、オンライン会議ツールもどう使っていいかわからなくて、最初はどうしようという感じでした。結局、授業開始は1か月遅れましたが、なんとかなりましたね。
【大下】その後授業形態が多様化しました。
【横内】大学院の授業も、海外からの中継にZoomを使うなど、対面だけでなくオンラインを活用するなどよい影響は残りましたね。
おふたりとも法政大学で長い間過ごされてきましたが、ご退職後のことをおきかせくださいますか。
【横内】私は18歳で大学に入って、それからずっと大学で過ごしてきたわけです。初めは大学生、次に大学院生、そして大学の先生。ずっと大学という場に支えられてきた人生でした。退職するとそれがなくなる、どうなるのだろう、というのはありますね。もともと先生になりたかったのだけれど、歴史が好きだったから、高校の先生、世界史の先生になるという感じで、大学の教員になってもやはり経済史、銀行の歴史を研究対象としてきました。教えるということよりも歴史が好きだったということが先かもしれません。教えるということはあまり得意でないのかなって感じはしています。退職したら教えなくてもいいので、今度は歴史のことだけができる。70歳以降は、今まで集めてきた本を読んで歴史そのものを楽しみたいですね。
【大下】私は会計を専門にしてきましたが、やはりお金の計算、数字を扱うのが好きなんですね。4月からは縁あって大阪学院大学の専任教員として大阪で教えることになりました。なので、しばらくは横浜と大阪を行き来することになりそうです。働いている方が健康にもいいですしね。
後輩教員や院生に何かメッセージはいただけますか。
【大下】若い時には退職したら旅行に行ったり、温泉巡りをしたりとかいろいろと考えていましたが、その時になったらあちこちガタがきて身体が動かなくなるんですね。だから思ったその時にとにかくやった方がいいですよ。
【横内】これが終わったらこれをやろう、あれが終わったあれをやろうと思っているとね、結局その時になると身体がいうことをきかなくなる。
【大下】飛行機の国際線なんかとても乗れない感じ。
【横内】自分で予約するなんて面倒くさい、一人で行くのも大変ってなってしまってね。
【大下】向こうで体調おかしくなったらどうしようかなんて。
(本日お見受けしている限り、お二人とも若々しく溌剌としておられますので大丈夫そうです。)
この度は、経営学研究科の変遷について貴重なお話をうかがうことができました。本当にありがとうございました。
おおした ゆうじ
法政大学経営学研究科 経理人コース、企業家養成コース、アカウンティング・ファイナンスコース
1983年4月~2025年3月
よこうち まさお
法政大学経営学研究科 国際経営コース
1992年4月~2025年3月
(2024年度研究科長 西川真規子によるインタビュー)