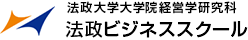企業家養成コース
企業家としての洞察力を徹底的に鍛える

企業家養成コースが開講されたのは 1992年であり、企業家の養成を目指すコースとしてはわが国初めてのものです。文字通り、企業家養成のイノベーターだと言えます。本コースでは、創業を志す人はもちろん、企業内で新たな事業や取り組みに挑戦しようとする人、事業の承継を志す人、企業家の支援に携わる人、社会問題の解決に取り組む人など、幅広い「企業家」を想定し、その洞察力を徹底的に鍛えられるよう、アカデミックの側からお手伝いをしていきます。
企業家が直面する状況は常に新しく、将来は常に不確実です。その中で的確な決断を下すためには、表面的・一時的な現象ではなく、本質を鋭く見通す洞察力が必須です。企業家養成コースでは、この力を磨くために、まずは経営学の基礎的かつ多様な考え方をしっかりと身に付けることを重視しています。 例えば、「ワークショップ」は、企業家本人の口から語られる経験を聴く場です。第一線で活躍している企業家をゲストとして招き、企業や事業を起こした経緯・動機、そのときの苦労や問題点、現在直面している経営上の課題や対応策などについてお話しいただき、議論を深めていきます。この双方向的な授業を通じて、参加者は語られる言葉の行間を読み込むとともに、企業家の置かれた立場を想像し、追体験しながら、企業経営の本質を考えることになります。
また、企業家活動、経営戦略論、イノベーション・マネジメント概論、企業間関係論、企業家史など、企業家の洞察力涵養に欠かせない科目も、 数多く用意されています。経営学は、時代の中で揺れ動く企業経営を冷静に見つめる、ダイナミックかつ挑戦的な学問です。長年にわたる経営学 の分厚い蓄積の中には、変わりゆく現実を論理的に分析するための有効なアプローチが数多く詰まっています。それを体系的に学ぶことで、企業家としての思考力を基礎から鍛えていきます。
2年次には、担当教員の集中的な指導を受けながら、アカデミックな修士論文を執筆することが学生生活の中心となります。この作業は、様々な科目の中で学んだ経営学のアカデミックなアプローチを自らの手で実践してみる作業にほかなりません。一見遠回りに見えても、論文を自分自身で執筆する経験を通して、企業家として必須である論理力・構想力が飛躍的に高まることになります。
毎年、本コースには多様な経歴の社会人が集まってきます。しかし、その全員が、ビジネスの現場で強い問題意識を持っているという点で共通しています。教員を交えてアカデミックな世界との対話を常に行いつつ、在学生同士がそれぞれの経験に基づき、多様なトピックについて実践的な議論を展開することも可能です。こうして育まれるネットワークは、さまざまな交流を通じて発展し、修了後も大切な財産となることでしょう。
教員紹介・担当科目(2024年度)
-

吉田 健二
教授
経営戦略論、企業家養成演習、経営学演習(昼間コース) -

金 容度(KIM Yongdo)
教授
24年度は担当科目なし -

近能 善範
教授
イノベーション・マネジメント概論、経営学概論(昼間コース) -

稲垣 京輔
教授
企業家活動、企業家養成演習、経営学演習(昼間コース) -

福島 英史
教授
企業家養成演習、経営学演習(昼間コース)、経営学基礎(夜間コース共通) -

二階堂 行宣
教授
企業家史、企業家養成演習 -

韓 載香
教授
経営史
学生の声
-
新しい挑戦で自分を変革できる2年間

林 輝夫
企業家養成コース
(2023年3月修了)ナブテスコ株式会社
私は現在、会社で新規事業開発を行なっています。世の中にイノベーティブな製品・サービスを届けることを目標に、HBSでの学び...
-
自分に必要な“何か”を得られる2年間

祭本 利樹
企業家養成コース
(2019年3月修了)サイモト自転車株式会社
私は大学卒業後、某企業を経験した後、家業を継ぐため現社へ入社しました。中国、日本各地での勤務を経てい...
-
全ての道は繋がっています。始めるなら今!
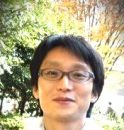
渡邊 一隆
企業家養成コース
(2017年3月修了)製造業
理工系の学部を卒業し、HBSの修士課程に入るまでいわゆる「理系畑」を歩んできました。その中で、企業が成長をして行く為に...
-
Think Different

清田 圭一
企業家養成コース
(2004年3月修了)TRIBASE, LLC. 代表社員
ベンチャーを起業する上でもっとも大切にしなければならないことはなんでしょうか。 それは、この事業を通じて、「どのよう...
-
コンサルタントとしての自分のキャリアを高める・・・

柴嵜 文彦
企業家養成コース
(2015年3月修了)日本マイクロソフト株式会社
進学のきっかけは、今の職場でIT戦略コンサルティング業務に従事したことでした。以前からビジネス書は読んでいましたが、本...
-
決断力を鍛えて、一生の企業家なかまを作る

山田 成徳
企業家養成コース
(2011年3月修了)株式会社バリュー・クエスト 代表取締役社長
私はeマーケットプレイス(インターネット上の企業間取引市場)を主事業とする会社を経営しております。会社の成長に伴って、...